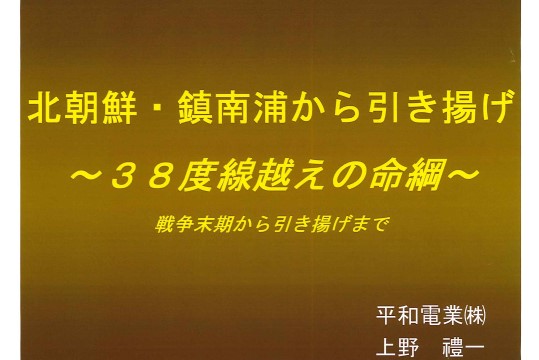
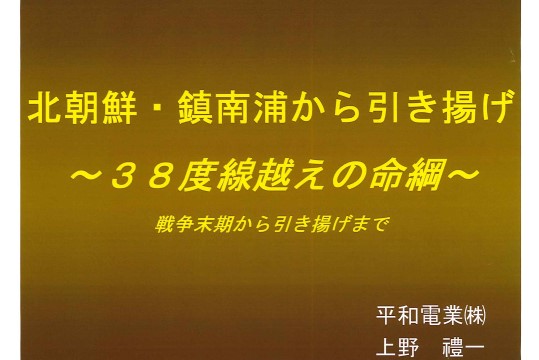 |
 |
| �����n�} |
 |
| �����n�}�ڍא} |
 |
| �J�[�`�XP51�퓬�@ |
 |
 |
| ������P�P | ������P�Q |
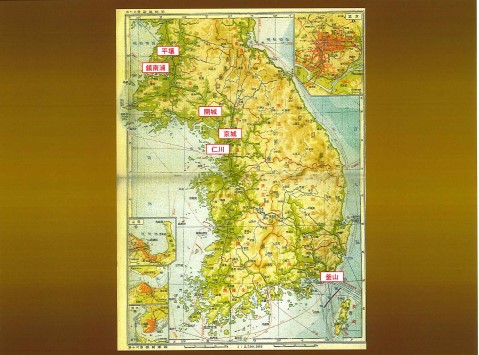 |
| ���N�����n�} |
 |
| ����Y�n�} |
 |
| ����Y�w |
 |
| ����Y�s�X�n |
 |
| ����Y�s���ʐ} |
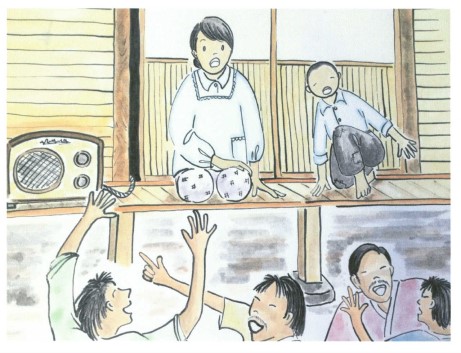 |
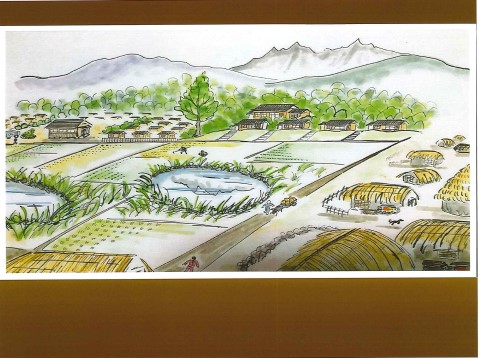 |
| �O�H�}�O�l�V�E���Б���ӕ��i |
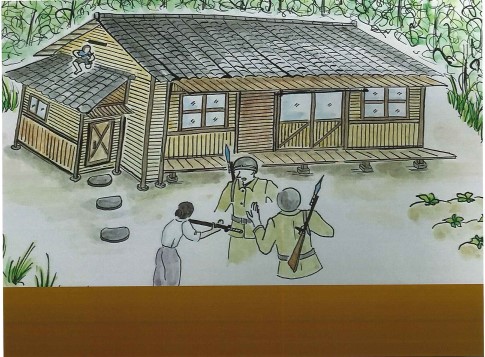 |
| �O�H�}�O�l�V�E���Б� |
 |
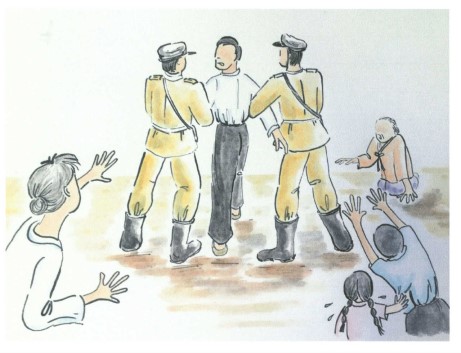 |
 |
| ����Y�w�Q |
 |
| ����Y�`���� |
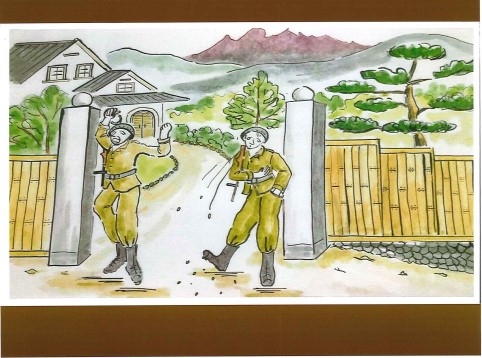 |
| �\�A����q |
 |
| �\�A�R�}���h�����e�i�y�@�֏e�j |
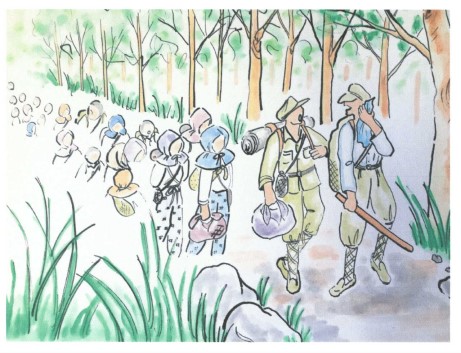 |
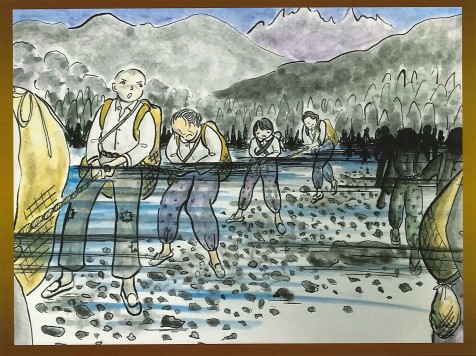 |
| �R�W�x���z���P |
 |
| �R�W�x���z���Q |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
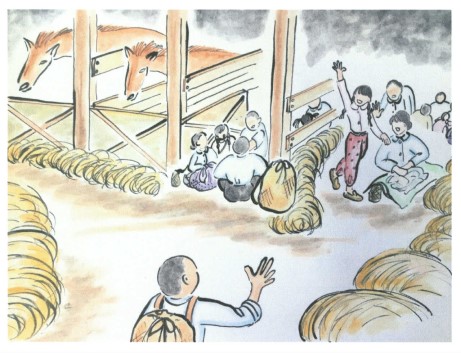 |
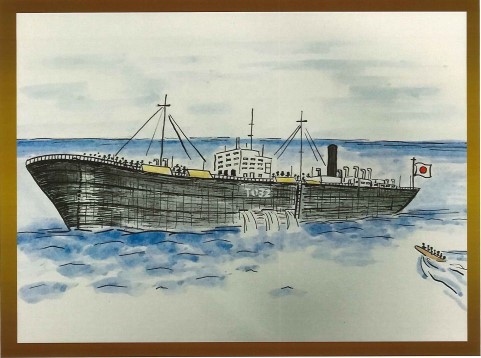 |
| �����g���D |